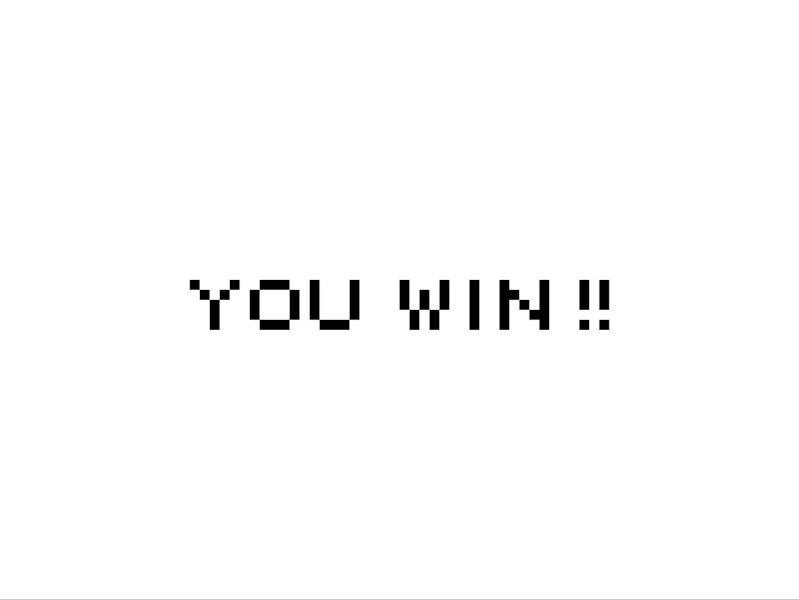
【格ゲー攻略への道】格闘ゲームで勝つための考え方【初心者】
格闘ゲームは他のゲームに比べて難しいという意見を聞きます。
コマンドの入力はその代表的な例で、たしかに波動拳コマンドの入力すら初めは難しいでしょう。
しかし、できるようになった時の喜びは努力した分大きくなります。
そういった壁を乗り越えていくことが、格闘ゲームの一つの魅力であることは間違いありません。
この記事は、格闘ゲームの一通りの操作ができるようになったけど何をすればいいのか分からない人に向けた内容となっています。
勝つためにはどうすればよいのかを整理し、考え方の参考にしてください。
勝つための助けとなれば幸いです。
1. 反応速度は誰でも大体同じ
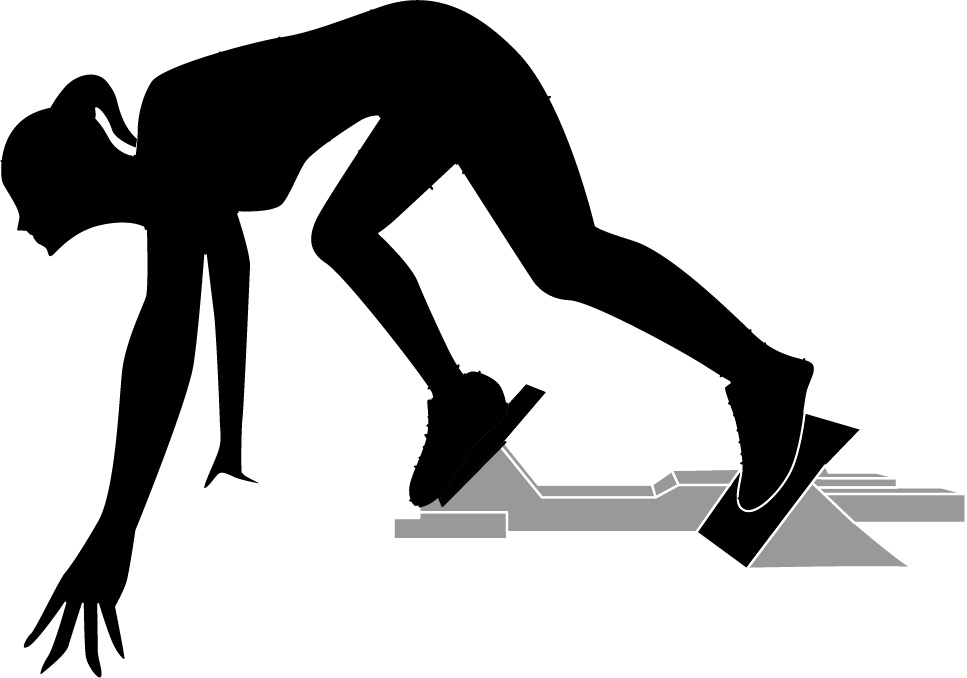
格闘ゲームをプレイしている人は、動画や他の人がプレイしている様子を見たことがあると思います。
そうして上級者のようになりたいというモチベーションを持つと同時に、人によってはどうして自分は彼らみたいに上手く動かせないのかと落ち込むことにもつながります。
中でも、あんなに早く反応できないと思うようなプレイを見て、彼らには特別な才能があって自分にはないのではないか、なんて考えを持つ人もいるかもしれません。
しかし、多くの場合そのようなことはありません。
人の反応速度は大体同じ程度です。
人間の平均の反応速度は、光の刺激に対しては0.18秒から0.22秒とされ、音への反応は0.12秒から0.18秒です。
また、陸上短距離での反応速度の限界は0.1秒とされています。
様々な条件をそろえていないものの、多くの人は0.1秒から0.2秒あたりであれば反応できるということです。
陸上競技のような、特定の刺激に対して反応の仕方を一つに決めた場合の反応にかかる時間を単純反応時間といいます。
単純反応は光や音を受けてから思考や判断をしない場合の反応です。
例えば赤い光を見たら止まる、青い光を見たら進む、黄色い光を見たら減速するという条件の場合は、反応が単純反応よりも遅くなるのは容易に想像できます。
その選択肢が多ければなおさらです。
格闘ゲームをプレイする上では、反応する対象を絞り、それに対して取る行動を定めておけばより早く反応できるということです。
波動拳を見た時だけ飛ぶ、という反応の仕方と意識を持てば、その意識がない時よりも格段に行動が速くなります。
これを知っておくだけでも上級者が特別でないと感じられるでしょう。
トレーニングの積み重ねで反応はより早くなります。
自分よりも反応の良いプレイヤーがいるとすれば、反応の練習を多く積んでいたからかもしれません。
(参考資料)
・全身反応時間の研究とその応用 - 日本スポーツ協会
・人はどこまで速く反応できるか 人知超越の0.001秒フライングでルール再考の必要性
2. 負ける原因を考える
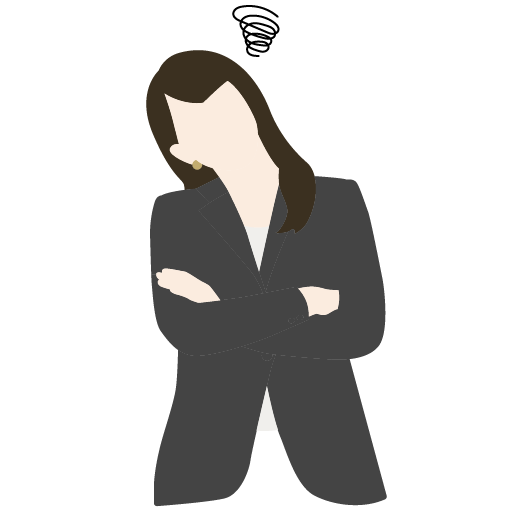
単純な反応速度にそれほど差がないのであれば、何が原因なのでしょうか。
具体的に考えてみましょう。
2-1. 何に困っているのかを特定する
試合を振り返ると、なんだか分からないけど色々されて終わった、という感覚であれば整理が付いていない状態です。
まずは何に困ったのかを見つけるところから始めましょう。
例えば、ステップからの投げを食らってしまう、相手の強キックをどうすればいいのか分からない、などです。
これを認識するのとしないのとでは大きな差があります。
2-2. 困ったときの状況を整理する
相手にされて困ったことを特定した後は、その時の状況をもう少し具体的に振り返りましょう。
どのような位置関係だったか、体力がどれくらいの時か、何の行動の後だったか、などです。
状況を整理すると思わぬ活路を見いだせるかもしれません。
簡単な例で考えてみましょう。
リーチの長い技を持つキャラに接近できなくて困っているとします。
体力差で負けているのであれば接近しなくてはいけませんが、体力が相手より多く残っている場合はそもそも攻め込む必要がありません。
安全にガードを続ければ時間切れで勝ててしまうからです。
行動自体が同じでも状況によってその行動の重要さは大きく変化します。
もしくは、相手の無敵技に当たり続けていたとしましょう。
相手の行動を落ち着いて見ると、突然技を出しているのではなく、隙が大きい行動の後に出しているかもしれません。
自分の不利な状況を分かっているからこその行動です。
気が付けばいつも二択を迫られているのであれば、その二択が成立するまでの過程をチェックしましょう。
崩される前の段階で出来ることがあるはずです。
このように、その時の状況を見返すと気付けることが多くあります。
最近の家庭用格闘ゲームにはリプレイ機能が付いているので、何度も見直してください。
3. 読み合いの選択肢をはっきりさせる

どのような状況で、何の技を出されると困るのかが分かると、読み合いという一つ上の駆け引きが始まります。
読み合いを成立させるために必要なことを順番に見ていきましょう。
3-1. 対処法を見つける
まずは相手の行動に対する何らかの対処法を見つけます。
対処法を見つけるにはトレーニングモードが一番です。
多くの格闘ゲームでは、CPUに一定の行動を記憶させられます。
これを活用して状況を再現しましょう。
初心者には最も難しく感じる行程かもしれません。
再現した相手の行動に対してあらゆる行動を試すと、思いもつかなかった選択肢が見つかることもあります。
対処方法は、一つではなく複数見つかるはずです。
最も簡単な例は、無敵技で返すというもの。
何にでも対応できるという意味では優れた選択肢です。
できる限り多く見つけられると、より上達します。
自分で見つけられない場合は調べたり、人に聞いたりして情報を集めましょう。
選択肢をまとめてリストにしておくと後で見直す際に便利です。
3-2. それぞれの選択肢のリターンとリスクを整理する
複数ある選択肢の内、どれが最もリターンがあるのか、どれが最もリスクが少ないか、などを整理しましょう。
無敵技で返す選択肢は、すぐに思いつけるところがメリットですが、リターンとして得られるダメージはそれほど高くありません。
また、ガードされた場合のリスクはとても高いはずです。
リターンが低く、リスクが高いのであれば、あまり良い選択肢ではありません。
他のより良いものを使いましょう。
リターンがとても高い選択肢は、多くの場合は難易度が高いものです。
失敗するリスクも考える必要があります。
3-3. ダメージを与えるだけがリターンではない
読み合いに勝つことと、ダメージを与えることはイコールではありません。
遠距離で戦うキャラと、近距離で戦うキャラの戦いを例に考えてみましょう。
近距離で戦うキャラが前に進むと、後々大きなダメージを与えられる可能性が高まります。
前に進めるだけでメリットなのです。
反対に、その相手からすると近づかれるだけでデメリットと言えます。
こちらのゲージを溜める行動も同じ様に試合を有利に進めています。
相手に直接影響を与えるだけが読み合いの勝ちではありません。
3-4. 最もリターンが高い選択肢と最もリスクの低い選択肢を練習する
全ての選択肢を整理した後は、最もリターンが高い選択肢と最もリスクが低い選択肢を練習しましょう。
体力が有利な時は安全な選択肢を、不利な時はリターンの高い選択肢を使い分けられるようになると勝率が上がります。
3-5. 相手の対応策を考える
ここまでのことができると、読み合いの選択肢はばっちりです。
しかし、相手はCPUではありません。
こちらの対応策に対して、新たな対応を取り始めます。
これに応じるために、あらかじめ相手の対応策を予想しておきましょう。
事前に準備しておくと、試合中にも臨機応変に対応できます。
4. 展開の速さについていけない場合

ここまで考えると、お互いの対応策がジャンケンのような関係になっていることが分かると思います。
グーに勝つにはパーを出さないといけないけどチョキを出されたら負けてしまう、といった感じですね。
しかし、いざ対戦となると落ち着いて考える時間はありません。
練習したことをやろうとしてもなかなか上手くいかないでしょう。
ですが、初めから思った通りに行動できる人はいません。
やっぱり格闘ゲームは難しすぎる!と考える前に、以下の項目を読んでください。
4-1. 全部に対応できる人はいない
全ての行動に対して完璧な対応ができる人はいません。
上級者と対戦しているとあたかもそんな錯覚を覚えてしまいますが、相手にそう思わせる技術があると考えてもいいかもしれません。
4-2. まずは一つの展開にだけ焦点を絞る
反応速度の話の際に、反応する対象を絞り、かつ取る行動を定めておけば早く反応できるとお伝えしました。
試合中は展開が速くて考えが追いつかないと思うかもしれませんが、全てに対応しようとせずに一つに狙いを定めてみましょう。
後だしジャンケンをイメージして下さい。
相手のグーとチョキとパーに対して毎回最速で勝てる選択肢を出すのは非常に難しく感じるでしょう。
しかし、チョキだけを待ち、チョキが来たらグーを出すと決めておくと速く反応できます。
その反応の速さに驚いた相手は、チョキは通じないと思うはずです。
それを見越して次は相手のグーかパーが来ると予想できれば、より有利に試合を展開できます。
このように、同時に複数のことをするのではなく、一つに絞って対応してみてください。
きっとできるはずです。
慣れてくると複数の選択肢にもある程度対応できるようになります。
4-3. 一つの展開に絞らせない
せっかくなので逆の立場から考えてみましょう。
相手がこちらの特定の攻撃に備えている場合、相手の予想を外した行動を取れば反応は遅くなるはずです。
相手がチョキに対してグーを出す意識を持っていると読み取れたのであれば、こちらはチョキを出さずにグーとパーを出し続ければいいわけです。
予想を外されると、普段は通らない攻撃があっさり決まります。
何度もグーとパーを出された相手はどうしてもグーとパーに意識が向き、チョキに対してはなかなか意識を割けなくなります。
そうなった頃合いを見計らってチョキを出せれば完璧です。
5. まとめ
格闘ゲームは個人と個人の戦いで、なおかつ勝敗がはっきり付きます。
ゲームとはいえ、自分の改善点を見つけ克服していく過程はある程度のストレスは避けられません。
それでもゲームは本来遊ぶためのものです。
あまり溜め込みすぎずに、勝利するまでの過程を楽しみましょう。
