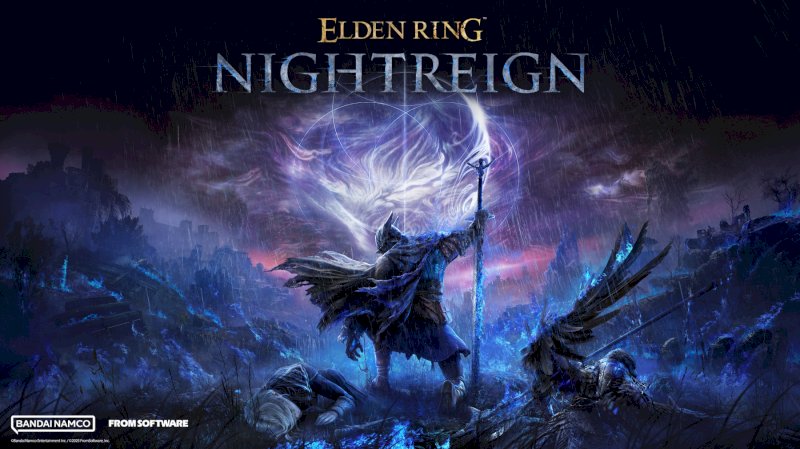
エルデンリングナイトレイン 隠者は玄人向け? 高火力キャラの立ち回りも徹底解説!
エルデンリングナイトレインはリリースから2か月余りが経過した作品ですが、強力なボスの実装などで多くのユーザーが繰り返し楽しまれています。
全8キャラが存在していますが、その中でも特に覚えることが多いものの、扱えれば高火力が期待できるのが隠者です。
ダメージソースとして大いに貢献できますが、覚えることも多いですし、「自分には扱えるか不安」など、挑戦したいと思いながらも躊躇ってしまう方もいるでしょう。
そこで本記事では、隠者の基礎や実践運用をはじめ、玄人キャラなのかについても解説します。
1. 隠者の基礎
https://game8.jp/eldenring-nightreign/687653
隠者は高火力を叩き出せるダメージディーラーですが、高いダメージを生み出しているのは当然基礎的な部分がダメージ寄りで構成されているためです。
ナイトレインでキャラの基礎を司るのが「アビリティ/スキル/アーツ」であり、実践運用を目指すなら必ず押さえておきたい要素となります。
そこでここでは、隠者の基礎となる「アビリティ/スキル/アーツ」を紹介します。
1-1. アビリティ:元素制御
隠者のアビリティである「元素制御」、これは隠者が魔法を放つために必要となる「属性痕」を相手に付与できるというものです。
魔法攻撃と属性痕の関係性については後にスキルで説明しますが、隠者の根幹を成しているアビリティと言えます。
また、後述するスキルで属性痕を回収する際にFPも回復できるため、アーツ等の使用に不可欠なFPを自給自足できる点は非常に優秀です。
ただし、敵に付与できる属性痕は自由に選択できるわけではなく、最後に自身が当てた魔法属性に左右される点には要注意。
炎属性魔法のヒット→炎属性痕を付与、雷属性魔法のヒット→雷属性痕を付与となるため、複合魔法等で欲しい属性痕があるなら、狙いの属性魔法を当てる意識が大切です。
1-2. スキル:混成魔法
https://gamewith.jp/eldenring/484974
「混成魔法」はアビリティ「元素制御」で付与した属性痕を最大3つまで回収でき、回収した属性痕を消費して魔法を放てるスキルです。
消費する属性痕の組み合わせは1~3属性を任意で選択でき、消費する属性に応じてヒット数やバフ/デバフが変化します。
雷属性のみだと回避アクションが強化され、聖属性のみだと強靭度とカット率の上昇、炎属性のみなら持続ダメージを与える炎を展開することが可能です。
魔力+炎なら多段ヒットの爆発、炎+雷なら火球となって突進しつつ雷を落とし、雷+聖なら攻撃を自動パリィできる鎧が纏えます。
3属性の混成魔法の場合、属性痕のストックを全て消費してしまうのは痛手ですが、大ダメージやHP回復、さらには無敵化と強力な効果が期待できます。
混成魔法の組み合わせは総数10を超えるので覚えるまでは大変ですが、上手く扱えれば攻守&サポートの全てを担える優秀なスキルです。
1-3. アーツ:血魂の唄
https://kamigame.jp/nightreign/page/356614090061297632.html
隠者のアーツ「血魂の唄」は使用時、自身を中心とする周囲の敵に「血の烙印」を付与し、「血の烙印」が付与された敵に対する与ダメージが1.15倍に上昇します。
さらに「血の烙印」が付与された敵を攻撃時、HPとFPも回復するため、ダウンのリスクを気にせずに高火力を叩き込むチャンスが狙えます。
また、ダメージ上昇効果及びHP/FP回復効果は隠者だけに留まらず、「血の烙印」が付与されていれば味方全員が恩恵を受けられる点が非常に優秀です。
「血の烙印」の付与時間は14秒とやや短めなものの、14秒の間に集中攻撃を叩き込めれば、チームが有利に立てることは間違いありません。
ただし、ダメージ倍率上昇や回復効果は得られるものの、相手を行動不可やスタンにできるわけではない点には要注意です。
倒されない位置取りを意識しつつ、高火力を叩き込んでHPやFPを同時に回復する狙い方がおすすめです。
2. 隠者の実践運用で意識したい点
https://gametokka.com/eldenringnightreigncharactor021725/
隠者は混成魔法による多彩な攻撃手段を持ち、アーツを使用すればさらに火力を伸ばしつつ、味方へのサポートも行うことが可能です。
攻守だけでなく、サポート性能も備えたポテンシャルの高さは強力ですが、10を超える魔法の組み合わせを覚える必要があり、実践運用は難しそうと感じる方もいるでしょう。
そこでここでは、隠者を実戦で運用するにあたって、意識したいポイントを解説します。
2-1. 主力となる魔法構成は覚える
https://gamerch.com/nightreign/924067
隠者はスキル「混成魔法」+アビリティ「元素制御」により、多彩な攻撃手段を行使できる点が強力です。
しかし、全ての属性構成を覚えようとした場合、10種以上を把握しておく必要があり、実践中に困惑してしまう恐れがあります。
自身が危機的状況に陥ったり、味方が危うい状況に陥った際、効果的な魔法を即座に放てないのは致命的と言えるため、これだけは確実に回避したい事象です。
そこで全ての属性構成を叩きこむのではなく、高頻度で使用したい属性構成のみを把握しておくのがおすすめです。
高火力を叩きこめる属性、無敵やパリィで守りを固められる属性、デバフを付与して行動を阻害する属性など、数ある中から主力級の構成を覚えておきましょう。
ただし、属性痕は味方の属性攻撃でも付与され、常に任意の属性を確保するのは困難となるため、全属性を含む混成パターンは最低1つは覚えておくのがベストです。
2-2. 基本的に後方で立ち回る
隠者は属性痕を回収し、回収した属性を組み合わせて魔法を使用するため、基本的な流れは「属性痕回収→混成魔法の発動」このループとなります。
この流れをスムーズにループするにあたって、危機的な状況に陥ることは必ず回避しなければいけず、基本的には後方で立ち回ることが重要です。
また、隠者は知力と信仰ステータス=Sと高めですが、HP/筋力/スタミナのような近接の立ち回りで重要なステータスは軒並みD~C程度しか備えていません。
つまり、近接での無理な立ち回りは事故が起きやすく、安定して属性痕を集められないどころか、自身がダウンしてしまうリスクもあるということです。
混成魔法の中には敵に接近するタイプの魔法もあるため、これらによる接近は例外と言えますが、基本的には後方で安全に立ち回る意識を持ちましょう。
2-3. FPが切れないように意識
隠者は属性痕の回収時にFPも回復できるため、一見するとFP切れは起きにくいと思われるかもしれません。
しかし、調子に乗って魔法を連発しているとFP切れで行動できなくなることもあり、FP残量は常にチェックしておくのが大切です。
FP切れを起こした隠者は攻撃もできなければ、バリア等の魔法でサポートもできず、チームが1人欠けてると言っても過言ではありません。
残された味方が苦しくなってしまうため、常にFP残量をチェックし、余裕を持って立ち回る意識がベストです。
3. 隠者は実際に玄人向けなのか
https://news.yahoo.co.jp/articles/a9ed081698d3868bf951f862dde77e2362ba43ad
隠者はさまざまな混成パターンを覚える必要はあるものの、基本的に後方での立ち回りとなるため、一見するとラクに思えるかもしれません。
ですが、プレイヤーの中には玄人向けという意見も多く、実際に玄人向けで運用が難しいのか、気になる方も多いでしょう。
そこでここでは、隠者は実際に玄人向けのキャラなのか、この点を解説していきます。
3-1. 慣れるまでは魔法が複雑で難しい
隠者の混成魔法のパターンは総数14種存在しており、単一属性~3属性の組み合わせ次第で効果が大きく変化します。
状況によって最適な魔法属性は常に変化するため、後方で属性を回収しつつ、適切な魔法を放つ必要があるのです。
敵の攻撃を見極めつつ、欲しい属性痕の回収も同時に狙い、さらに魔法の組み合わせまで意識が必要となります。
慣れれば最適解で魔法パターンを見抜いていけますが、慣れるまでは混成魔法が足枷になってしまい、全ての行動パターンが遅れてしまう可能性もあります。
何度も繰り返し慣れることでポテンシャルは引き出しやすいですが、慣れないと強みを活かしにくいという点では玄人向けと言えるでしょう。
3-2. 距離感を保つのが難しい
https://news.yahoo.co.jp/articles/a9ed081698d3868bf951f862dde77e2362ba43ad/images/002
隠者は後方から属性痕を回収し、回収した属性痕を組み合わせて混成魔法を放つため、基本的に後方で立ち回ることとなります。
また、戦い方だけではなく、HPやスタミナ等のステータスも軒並み低いため、敵の攻撃を1回受けるだけでも致命傷になりやすいという理由も含まれています。
しかし、3人パーティで挑んでいる状況であっても、敵からのヘイトが隠者に向くことも当然あり、そうなった場合も適切な距離感を維持するのは非常に難しいです。
適切にバリアを展開できる魔法を使用したり、迅速に引けるなら問題はありませんが、慣れるまではテンパってしまいやすいです。
こればかりは隠者を使い続けて感覚を養うしかなく、初心者では扱いにくいという点から玄人向けとされています。
4. まとめ
隠者を扱うには最低限使用頻度が高い混成魔法を把握する必要があり、適切な距離感も同時に維持する必要もある難しいキャラです。
ですが、扱えるようになれば高火力を連発できたり、味方のサポートも行えるやりごたえも感じることができるので、一味変わったプレイを求めるならチャレンジしてみてくださいね。
